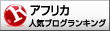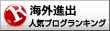★目次★
こんにちは!Pick-Up! アフリカです。本日は、ルワンダと日本の架け橋となり、教育支援を行うルワンダの教育を考える会を運営する永遠瑠マリールイズさんをご紹介します。インタビューでは、ジェノサイド当時の話や活動への想いを語ってくださいました。
ぜひ最後までご覧ください!
ルワンダの教育を考える会のインターンシップとは
| 場所 | キガリ(ルワンダ)、福島(日本) |
| 時期・日数 | 年中募集、詳細は相談 |
| 費用 | 状況に応じて相談 |
| 内容 | ◎「ルワンダの教育を考える会」やルワンダについて発信する広報活動 ◎ルワンダにおける農村地域の貧困家庭に対する支援活動 ◎ファンドレイジングの企画や応募 ◎現地の支援活動への同行 ◎イベント企画 ◎「ルワンダの教育を考える会」が運営する現地の幼稚園・小学校との話し合い |
| 歓迎 | ・情報発信や企画能力がある人・ルワンダ・ジェノサイドの語り部になってくれる人 |
| HP | https://www.rwanda-npo.org/ |
代表・永遠瑠マリールイズさんプロフィール

名前:永遠瑠マリールイズ
学生時代にJICAのプログラムで日本に留学。ルワンダに帰国後、ルワンダ・ジェノサイドが発生。子ども3人を抱えたまま難民キャンプに避難し、生死寸前で虐殺から生き延びる。その後、日本とのご縁で非営利団体「ルワンダの教育を考える会」を設立し、現在は福島県を拠点に活動を続けている。
──NPOを設立された目的を教えてください。
インタビューへの想い
ルワンダと聞いて、まず思い浮かぶのはジェノサイドかもしれません。しかし、なぜジェノサイドが起きたのか、がわからないので誤解してしまう方もいらっしゃるのです。
(ガイドブック掲載のため、)日本のバックグラウンドを持った方々にインタビューされると思いますが、ルワンダのバックグラウンドを持って日本で活動している、 なおかつルワンダでも活動しているのは、私ぐらいじゃないかなとは思います。私が全て知っているわけではないのですが、これを読んだ方にルワンダのことやジェノサイドのことについて少しずつわかっていただけると嬉しいです。
ルワンダの伝統的な考え方
ルワンダに渡航されたことがある人はご存じかもしれませんが、ルワンダの人々がフレンドリーなことは自慢できることの1つです。ルワンダには「友達は宝だ」という考えがあります。ですから、友達になったら兄弟みたいに、年上の方なら尊敬する自分の両親と同じように接するのです。
ルワンダには昔から資源もあまりなかったけれど、お互いに助け合って生きてきました。もちろん喧嘩することもあるけれども、喧嘩をしたら縁を切るというようなことはなくて、喧嘩した原因をなくすために謝って仲直りして、共に歩んできたんです。
ジェノサイドのイメージが強いから、そのイメージのままルワンダに来て警戒される方もいるかもしれませんが、ルワンダの人々はないものの中から助け合いながら生きてきました。家の料理用の水が足りないとなれば隣の家の人がわけてくれる、近所の人が病院にお見舞いに行くとなれば代わりに食事をつくる、そんな国でした。
ルワンダに来たら国境を見てほしいんです。国境を接する国が4つありますが、どの国とも明確な分かれ目がなく内陸続きのようになっているんです。ブルンジでは通訳なしで言葉も通じるので兄弟のように感じていたんです。
植民地をきっかけに変わるルワンダ社会
そんな助け合いの社会も植民地をきっかけに割かれてしまったのです。
ベルギーの植民地時代には、身分証明書が発行されて、兄弟だった人の所属する続柄が変わってしまったり、同じ両親を持つ子どもたちが持っている財産によって民族をわけられてしまったり、多くの人々がある一部の人々によって教育から遠ざけられてしまったりしました。
教育を受けることができる少数の人々が、教育を受けることができない大人数を抑えつけたらみなさん反発しますよね。私は運よく教育を受けることができましたが、周りの仲間たちの中には教育を受けたくても受けることができなかった者もいました。同じ仲間に「いいな」と言われながら教育を受けていたあの時は、子どもながらにすごく嫌でした。みんなが教育を受けていたらあんな事件は起きなかったのではないかと今になって思います。なので、そういう状況を私の子どもにも、孫にも残したくないというのが私の根幹にあります。
ジェノサイドで感じた教育の重要性
93年に、ルワンダでJICAの青年海外協力隊の方々と出会ったことがきっかけで、日本に留学生として来るように推薦をいただいて日本語の勉強をしました。
94年に帰国すると、あのジェノサイドが起こりました。私は6歳、4歳、2歳の子ども3人を連れて、爆弾が行き交う中、難民キャンプを目指しました。
難民キャンプに向かう途中、子どもたちが横たわって死にそうになっているのを見て、ある若者がパンを売ってくれたのです。自分も何もないんだけど、でも横たわって死にそうになっている子どもたちに持っている最後の蓄えを渡す…ルワンダの人々の心のやさしさに触れた瞬間ですね。
私はそのパンを高く買ったんです。でも賞味期限が切れていてカビだらけのパンでした。これを食べて生きるか、死ぬかという選択を迫られました。結局私たちはそのパンを食べて、でもお腹が満たされると人間また活力がみなぎるんですね。奇跡的に誰も死なずに、コンゴ民主共和国の難民キャンプまで辿り着くことができました。
難民キャンプに着くとそこには小麦粉がありました。それを見て私は、ドーナツがつくれる!とひらめいたんです。それから、私が朝早くドーナツを作って6歳の子どもが売って…ドーナツを食べたくて食べたくてしょうがなかったけど、売り物だから食べられなかった。でもその売り上げが私たちを救ったんです。これは私が中学校の家庭科の調理実習でやったことがあったから思いつくことができたんです。
そして、日本にいたときのホストファミリーに「生きています。難民キャンプにいます。助けてください。」とひらがなで手紙を書いたんです。日本の難民を助けに来ていたドクターたちがその手紙を見て、難民キャンプでの通訳の仕事を頼まれました。そして、日本にいた時の皆様の尽力により、再び日本に留学生として来ることができました。長いお話でしたが、このような経験があって私は、教育があればどんな状況からでも生き返ることができると確信したんです。
だから、ルワンダに必要なのは教室で学ぶこと。 学んで自分らしく生きられる人になったら、人の痛みもわかる。 仲間意識もできる。そこから、 一生懸命働いて、一緒に国をつくっていこうという気持ちにもなるので、ルワンダの方々に教育を届けるために。ルワンダの教育を考える会を立ち上げたわけです。
NPO立ち上げのエピソード
立ち上げるときは周りから猛反対されました。当時、学生で働いていなかったので、生活が苦しく活動資金がなかったんです。みんなから反対される中で、1人だけ賛成してくれる人がいたんです。それは、私の日本留学を手配してくれたおばあちゃんでした。
専門学校の理事長をしていた彼女は、私にこんなことを言ったんです。「ルワンダのことを知っているのはマリールイズしかいないですよ。子どもの成長は止まらない、状況がよくなるまで待っているうちに子どもは成長してしまいますよ。やるなら今しかないですよ。今なにもしなかったら、また同じことが繰り返されるのよ。だからみんなが反対してても、私は味方だから。」って。
この言葉に救われたんです。だから皆さんも誰かの味方になってください。1人でも応援してくれる人がいれば、この人が信じてくれているから頑張ろう、って思えるんです。
そこから、いろんなところに行って講演をしたり、料理教室をしたりして少しずつお金を貯めていきました。5万円貯まれば、ルワンダに送って学校に行けない子どもたちのためのサポートをしました。法人格が取れて、福島県で初めての国際協力、国際支援をするNPOとして誕生しました。
NPOの目的は、『戦争で傷を負ってしまった子どもたち、夢も希望もなくしていた子どもたちに、希望と夢を取り戻したい。』というものです。その子どもたちが希望を持ったら、間違いなくルワンダの平和のために働くと思うので、そのために様々な支援を行っています。宗教とか民族とか政治とか、そういうことに気をとらわれず、自由に、いろんなものを見て、いろんな気づきをして、いろんな進路に進んでほしいという思いを込めています。
最初は4人から始めました。「味方だから」と言ってくれた理事長と、理事長が言うんだったらと加わってくれた2人と、私の合計4人でした。そして、イベントも何もやったことがないのに、アフリカのミュージシャンを呼んでホールをいっぱいにして、そのコンサートに来た人たちが会員になってくれました。
子どもたちや主人の理解があって、私が得る収入はルワンダの貧しくて学びたくて学べない子どもたちのために使わせていただいて、主人の稼ぎだけで生活していました。こういった家族のサポートがあったからこそ、NPOが誕生しました。
活動に関して
学校を建てるだけではなくて、通う子どもがいるものが学校だと思っています。教室に子どもがいなければ、建物がどんなに立派でも意味のない建物になってしまうので、そこに子どもが確実に通ってこれるようにするのが、私たちNPO法人の役目です。
ルワンダの子どもたちに対して教育支援をするために、命の尊さ、教育と平和の大切さをテーマに、全国各地で年50回から100回くらい講演をしています。そこで、ルワンダのことや活動のことを理解してもらい、ルワンダの教育を考える会に加わってもらうよう呼びかけています。
他にも、ルワンダ産のコーヒーや紅茶を販売するようなイベントを開催して募金を呼びかけています。あとは助成金や補助金に応募してお金を集めています。その集まったお金で学校建設や、最も貧しい家庭の子どもたちに教育支援を行っています。
また、同時に健康プロジェクトも行っています。学校に通うためには健康でなければならないからです。ルワンダには日本の児童・生徒が毎年受けるような健康診断がなかったので、ルワンダで導入しました。そのために、日本のドクターをルワンダに呼んで、ルワンダのドクターと一緒に学校健診をつくりました。私たちがサポートしている地方の学校の子どもたちに年に一回健康診断をしてもらっています。
健康診断をして栄養失調だとわかった子どもたちには給食を提供しています。加えて、妊婦さんと母乳を与えているお母さんに、定期的に5つの穀物が配合されている栄養バランスの取れた粉を毎月提供しています。これにより、子どももお母さんもどちらも健康になることを目指しています。
この健康プロジェクトでは現在28世帯を支援しています。きっかけは、とある印刷会社に行き、ルワンダの教育を考える会と書いてある名刺を渡した際にそこにいたスタッフから「うちの子どもたちの教育も支援してよ!」と言われたことでした。その子どもたちに会いに行くことになって、ルワンダに何年も住んでいた私ですが初めて、村に行きました。そこには標高が高くて寒さに震えている子どもたちがいたんです。親は見当たらなくて、お腹はふっくら出てるけど、もうげっそりしていて、いつ洗濯したかわからないような服を着ていました。
私自身も4人子どもを育てた経験があるので、見てすぐにこの子たちは栄養失調だとわかったんです。お昼御飯用に持っていったパンを子どもたちに渡して、その日は家に帰りました。
家に帰っても、食事が喉に通らなかったんです。 悲しくて悔しくて、この子どもたち、何もしなかったら、本当に大人になれないんじゃないかなって思って、すぐに私の持ってるお小遣いは、もうこの子たちの一日のおかゆにするって決めたんです。
周りの人には急な新しいプロジェクトについて反対されましたが、「子どもたちがこのように貧困のままだとまた戦争が起きるんですよ」と説得しました。
加えて、親へ支援をしなければ、親と子の共倒れとなってしまうと感じたので、お父さん・お母さんの意識改革を始めました。もともと彼らは狩猟採集で生きていたのですが、彼らにも普通の生活をしてもらうためにと、政府が家を建てて畑用の土地を与えたんです。でも、一度も畑を耕したことがなく、家に住んだことがない人たちに普通の生活をしろっていうのも無理な話で、家の柱を燃やして暖をとっていたみたいなんです。行政にもお願いされて、彼らの支援を行うようになって、今では完璧ではないですが、時期になれば畑を耕して種まきをするようになりました。その後、行政に働きかけて学校を作ってもらったのですが、子どもたちが通えるようにするため支援も行っていました。
もう一つ、コミュニティデベロップメントも行っています。子どもの支援は永遠にできるわけではないから、親御さんが自分の子どものために授業料を出せるようになるための様々な支援をしています。農業や洋裁を教えて、物乞いをしていた人が今では自分で作って収穫したものを食べていけるようにしています。
日本の方々に伝えたいこと
──日本の方々に向けて伝えたいことを教えてください。
この思いを次の世代につなげていくことが、一番大事なことだと思っています。
世の中から弱い立場の人がいなくなることはありません。だから、困っている人がいたら「誰かがやってくれる」ではなく、「自分がその主役なんだ」と思ってほしいんです。社会の問題を解決するために、誰かに任せるのではなく、自分には何ができるかを考えてほしい。
私たちは年を重ねますが、私が30年前に体験したことを今の若者に経験してほしくないし、繰り返してほしくない。だからこそ、若い皆さんに現状を見て、この活動を続けてほしいと願っています。
平和の大切さも受け継いでほしい。今こうしてオンラインでつながれるのも平和だからこそです。平和は誰かが作ってくれるものではなく、自分がどう行動するかが大事です。
日本の若者もルワンダの若者も、世界中の若者も、平和は自分たちのものだと考えてほしい。ニュースで見ているウクライナの戦争では、若者が戦い命を落としています。夢を持っていた彼らが、その夢を奪われてしまったのです。
戦争は大人が作り出すもので、戦う子どもたちは敵でもないのに殺し合いに巻き込まれています。これはとても悲しいことです。
だからこそ、若者には「夢を見るために生まれてきた。殺されるためではない」と知ってほしい。それを次の世代へ伝え続けていくのが、私たち「ルワンダの教育を考える会」とマリールイズの願いです。
平和のために生きてほしい。戦争をせず、死なないでほしい。その思いを多くの人に伝えたいと思っています。
今の日本の皆さんも、当たり前の毎日を大切にしてください。平和が失われれば、最悪の時代が訪れます。私たちは戦争を経験してほしくありません。
平和教育の活動を通じて、皆さんと一緒にこの呼びかけを続けていきたいと思っています。
ルワンダの教育を考える会を通じて現地で体験できること
──ルワンダに訪れる際には貴団体でどのようなことができますか?
来られる日数や予算によって、見られる場所や内容が変わってきます。
私たちは学校もいくつか持っていますし、ミヨベやブササマーナなどのコミュニティもあります。さらに南の方にも新しいコミュニティを作っています。日程によって、全部まわることもできますし、もし日数が少なければ近場だけしか見られないこともあります。
また、その地域の活動にも参加できます。たとえば、医師や看護師の方が来て健康診断をしているときには、そのイベントに参加していただけます。
子どもたちとのミニ運動会なども企画可能で、参加したい方がいれば一緒に楽しむこともできますし、色々な形で関われるようにしています。
観光も希望があれば対応します。例えば、アカゲラ国立公園(サファリを楽しめる観光地)に行く場合は、現地のオフィスが手続きやアテンドをしてくれます。
現地事務所の訪問方法
──訪問の際の連絡方法を通じて教えてください。
HPのお問い合わせからという形になります。また、私(マリールイズさん)が8月20日から9月の29日までルワンダに滞在しているので、その期間は私が現地で講演をすることもできるし、案内をすることもできます。
毎年8月15日にはピースコンサートを開催していますので、その準備をお手伝いしていただくこともできますし、政府関係者の方の講演会に参加していただくこともできます。
日本事務所・ルワンダの現地事務所のインターン
──インターンなどは常時募集しているのでしょうか。
日本の事務所では、活動を発信してくれる人が常にほしいです。特に広報に強い方がいらっしゃったらぜひ参加していただきたいですね。また、イベントを行うために企画が強い人、会計管理ができる人、あるいは、ルワンダのことを理解して自分が語り部となって発信してくれる人に参加してほしいです。
現地の事務所でインターンするのであれば、スタッフと一緒になって日々の業務をやってもらいます。支援している学校との話し合いをしたり、現場の活動に行ったり、非電化世帯に太陽ランプを届けるプロジェクトに参画したり…あとはファンドレイジングですかね。
──インターンではどういった費用がかかってくるのでしょうか。
食費や宿泊費、移動費はご自身で負担していただく形となります。また、何か企画をしたり、計画を立てたりする場合にはスタッフをつけなければならないので、そのための費用をお支払いしていただく可能性もあります。詳しくはご相談ください。
Pick-Up! アフリカを運営しているレックスバート・コミュニケーションズ株式会社では日本企業のアフリカ進出をサポートしています。
気軽にお問合せ、ご相談ください!

ご相談・お問い合わせ
アフリカ・ルワンダへのビジネス進出をご検討の際は、当サイトの運営に関わっているレックスバート・コミュニケーションズ株式会社までご相談・お問い合わせください。